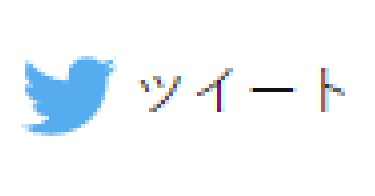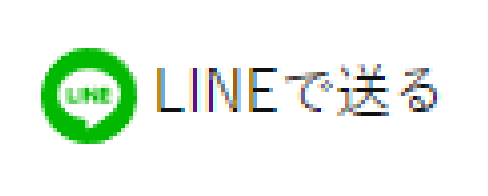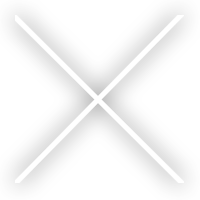陶房内にあるガス窯。盆器はこの窯で焼かれている。隣村に薪の窯もあるので、磁器・陶器、酸化・還元とあらゆる焼成方法が可能。

釉薬はすべてオリジナルで、数百という種類をすべて自社で作り、保存しているという。

胎土は歴代飛騨の土を使う。窯としての伝統とこだわりは、粘土や釉薬の原料としての土、木灰、そして鉱物にまで及ぶ。
渋草焼と柳造窯の歴史
江戸末期の天保12年(1841)、飛騨高山の「渋草ヶ丘」という地に尾張から陶工・戸田柳造を招いて半官半民の窯が開かれました。やがて地元で良質な陶石が発見され、また苦心の末に磁器焼成に成功、加賀九谷から絵付師を呼び寄せて五彩や南京赤絵、古染付写しなどの優品を作ります。「飛騨九谷」と呼ばれ全国に名を馳せますが、戸田柳造の死(1865)、江戸幕府の終焉(1867)によって支えを失い、衰退を余儀なくされます。明治11年(1878)、地元有志が経営を引き継いで再興。全国の有名窯の手法を取り入れて多岐にわたる製品を作り始めたこの窯は「芳国社(後に芳国舎)」と命名され、パリ万博への出品などにより世界的な知名度と人気を獲得していきます。
明治18年(1885)、「芳国社」の熟練工3名が工房を離れて独立、その中の松山惣兵衛が二代目戸田柳造を襲名します。以降「渋草柳造窯」は陶祖・戸田柳造から連なる伝統を踏まえ、新たな渋草焼の世界を模索しながら、時代と共に名を高めてきました。